コラム
2025.04.17
ひとり親だからこそ知りたい「自分を変えられない」ときの心の仕組みと乗り越え方。子育てと仕事の両立のヒントを解説!
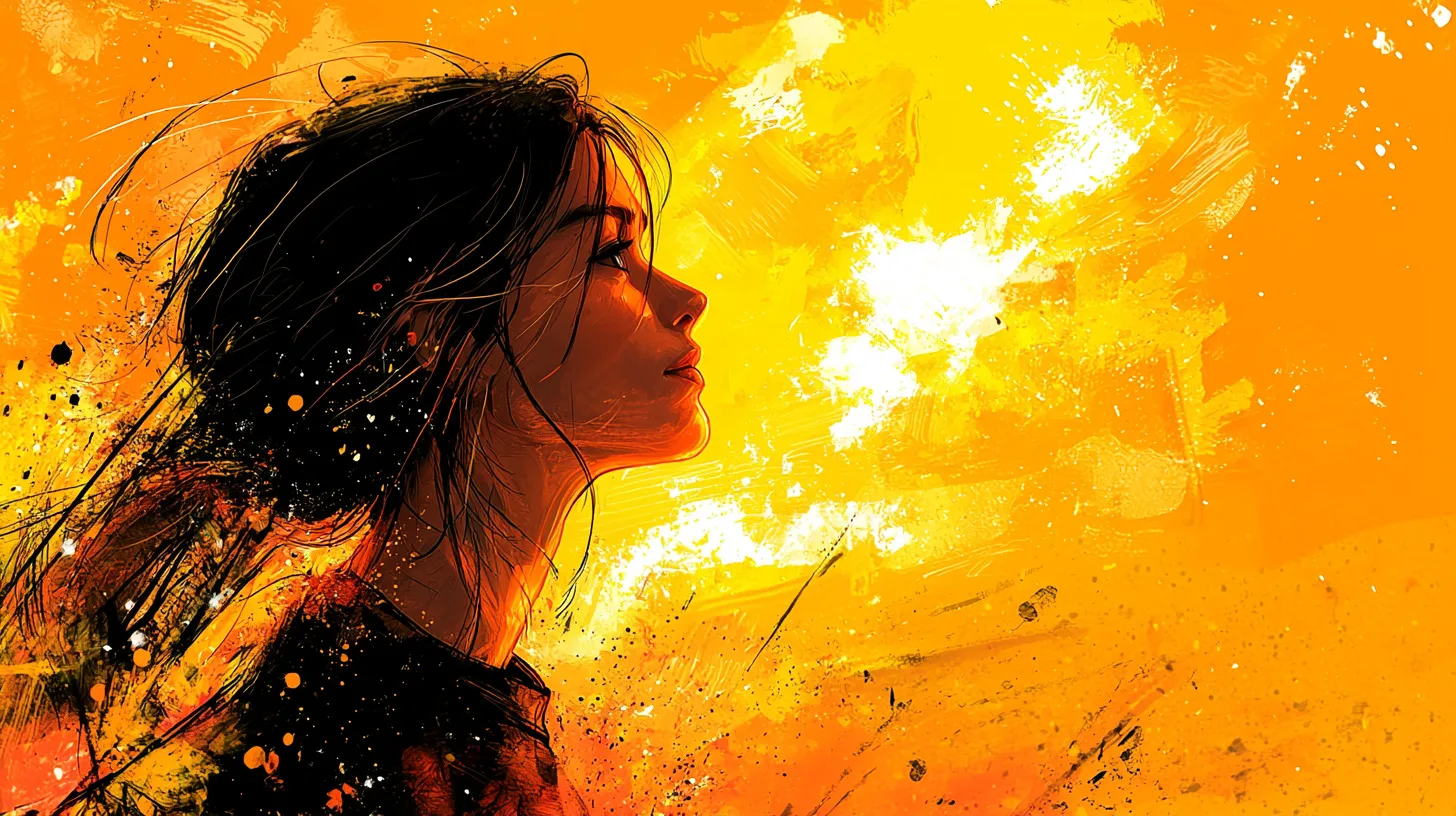
こんにちは。ひとり親の方限定のトークアプリ「ペアチル」のライターチームです。
今日は、ひとり親として「自分自身を変えたい」と思いながらも、なかなか行動に移せないときの心の仕組みについてお話ししたいと思います。
「子どものために頑張らなきゃ」「今は子どもが優先」と思いながら、気づけば自分のことはいつも後回し。そんな日々を送っていませんか?
ひとり親の皆さんは、子育てと仕事の両立に毎日奮闘しています。朝から晩まで忙しく動き回り、子どもが寝た後もぐったり疲れて、「明日からダイエット始める」「勉強を再開する」「早起きする」と思いながらも、なかなか実行に移せないことが多いものです。
そういえば、こんな言葉があります。「自分を変えられないのは、怠け心のせいではなく、心の仕組みのせい」だと[1]。なんだか少しほっとしませんか?
実は、自己変容(自分を変えること)を妨げる心理パターンには、いくつかの種類があるんです。そして、その心理パターンを知ることで、自分をむやみに責めることなく、小さな一歩を踏み出せるようになります。
この記事では、ひとり親が特に陥りやすい10の心理パターンと、忙しい毎日の中でも実践できる具体的な対処法をご紹介します。子育てと仕事に追われる日々の中でも、少しずつ自分自身を大切にする方法が見つかるはずです。
目次
- 「私には無理」とすぐ諦めてしまうとき ― 自己変容放棄型の心理
- 完璧を求めすぎて一歩を踏み出せないとき ― 完璧主義行動停止型の心理
- 大切なことを先延ばしにしてしまうとき ― 先延ばし(プロクラスト)型の心理
- 「どうせうまくいかない」と思い込んでいるとき ― 学習性無力感型の心理
- 情報が多すぎて混乱し、行動に移せないとき ― 情報過多混乱型の心理
- SNSの「完璧な親」と自分を比べて落ち込むとき ― 他者比較自己否定型の心理
- 「もう年だから」「才能がない」と思いがちなとき ― 固定的マインドセット型の心理
- 変化によって「自分らしさ」が失われる不安 ― アイデンティティ脅威型の心理
- 心も体も疲れ果ててしまったとき ― 燃え尽き症候群型の心理
- 理想と現実のギャップに苦しむとき ― 認知的不協和型の心理
- あなたの心理パターンを知って、小さな一歩を踏み出すために
- まとめ
ひとり親だからこそ陥りやすい「自分後回し」の習慣とその影響
ひとり親の方がついやってしまいがちなのが「自分のことは後回し」という習慣です。子どもの宿題を見てあげたり、お弁当を作ったり、仕事の準備をしたりしていると、気づけば一日が終わってしまいます。
ひとり親は二人親より「時間貧困(可処分時間が中央値の 50 % 未満)に陥る割合が高く、働くひとり親の約 30 %、女性に限ると 40 % が該当します(OECD‑ATUS2012)。これは単に時間の問題だけではなく、心の余裕も奪われていくことを意味します。
長く続けば続くほど、「自分を大切にする感覚」が薄れていきます。そして「自分を変えよう」と思っても、なぜか行動に移せない…そんな悪循環に陥りがちです。
「自分を変えたい」と思いながらも行動に移せない理由
「自分を変えたい」と思いながらも、なぜ行動に移せないのでしょうか?実は、私たちの脳は「変化」を危険なものと認識する傾向があります[3]。
特に日々の生活に精一杯のひとり親の方の場合、現状維持バイアスが強く働きます。「今は大変だけど、なんとかやれている」という状態を守ろうとするのは、脳の自然な防衛反応なのです。
また、変化を起こすには「認知的な余裕」が必要です。しかし、家事、育児、仕事と複数の役割を一人で担っていると、その余裕がなかなか生まれません。だから「今日は疲れたから明日」が繰り返されてしまうのです。
心理パターンを知ることで見えてくる、自分への優しい接し方
自分を変えられないときに「意志が弱い」「努力が足りない」と自分を責めても、状況は良くなりません。むしろ、自己嫌悪感が生まれ、さらに変化から遠ざかってしまいます。
大切なのは、自分の心理パターンを知り、その特徴に合った対処法を見つけること。そして、小さな一歩から始めることです。心理学研究においても、自己理解が行動変容の第一歩であることが明らかになっています[4]。
「完璧な変化」を求めるのではなく、「少しでも前に進む」ことを目指す。そんな優しい接し方が、忙しいひとり親の方にとって持続可能な自己変容への鍵となります。
「一人じゃないよ」同じ悩みを持つひとり親の方と今すぐつながれ、本人確認必須の無料アプリ(2,400名程度が利用中) >>
「私には無理」とすぐ諦めてしまうとき ― 自己変容放棄型の心理
「この英会話アプリ、毎日続けたいけど、私には絶対無理…」
「ダイエットしたいけど、三日坊主の私じゃどうせ続かない…」
こんなふうに、何かを始める前から「自分には無理」と決めつけてしまうことはありませんか?これは「自己変容放棄型」と呼ばれる心理パターンです。
子育てと仕事の両立で「これ以上は無理」と感じるひとり親の現実
ひとり親の場合、毎日の忙しさから「これ以上頑張る余裕はない」と感じることが多いものです。朝から晩まで子どもと仕事のことで精一杯で、自分のことを考える時間もエネルギーも残っていない…そんな現実があります。
国立社会保障・人口問題研究所の調査では、ひとり親の多くが「時間的余裕のなさ」を課題として挙げています[5]。このような状況では、新しいことを始めようとするエネルギーを見つけるのが難しいのは当然です。
「もっと頑張ればいいのに」と周りから言われても、すでに精一杯頑張っている現実があります。だからこそ、現実的なアプローチが必要です。
ワンオペ育児の中で小さな成功体験を積み重ねる方法
自己変容放棄型の対処法として、「マイクロゴール設定」という方法があります。これは、とにかく小さな、本当に小さな目標を設定するというものです。
たとえば、「毎日英語を1時間勉強する」ではなく、「子どもが寝た後に英単語を1つだけ覚える」というレベルです。たった1つでも構いません。そうやってハードルを思い切り下げることで、「できた!」という小さな成功体験を積み重ねていくんです。
研究によれば、成功体験は自己効力感(自分にはできるという感覚)を高め、次の行動へのモチベーションになります[6]。小さな成功体験を積み重ねることで、少しずつ「私にもできる」という感覚を育てていくことができるのです。
寝かしつけ後の「たった1分だけ」から始める自己変容のコツ
具体的な実践法としておすすめなのが「1分ルール」です。新しい習慣を始めるとき、「とりあえず1分だけやってみる」というものです。
たとえば、「英語の勉強」なら、「英単語帳を開いて10秒眺めるだけ」から始めるのもOK。「部屋の片づけ」なら、「一つだけものを元の場所に戻す」ところから。
この方法のポイントは、「できなかった自分」を責めないこと。まずは「できた!」という経験を積み重ねることが大切です。脳科学の研究でも、小さな成功体験が脳内の報酬系を活性化させ、次の行動へのモチベーションを高めることが示されています[7]。
対処法として効果的なのは:
- マイクロゴール設定: 1日1分、1個、1行など、極小の目標を設定する
- 共感的な自己対話: 「忙しいのに、よくここまでやってるね」と自分をねぎらう言葉をかける
- 小さな成功の記録: たとえ1分でも実行できたら、カレンダーに印をつけるなど視覚化する
「そんな小さな一歩で意味あるの?」と思うかもしれませんね。でも安心してください。小さくても続けることが、大きな変化につながります。まずは「椅子に座って課題を1分だけ見る」というところから始めてみませんか?
自己変容の道のりは、一人では孤独で険しいものです。ペアチルのトークアプリでは、同じひとり親だからこそ分かり合える仲間と出会い、互いの成長を支え合うことができます。
「一人じゃないよ」同じ悩みを持つひとり親の方と今すぐつながれ、本人確認必須の無料アプリ(2,400名程度が利用中) >>
完璧を求めすぎて一歩を踏み出せないとき ― 完璧主義行動停止型の心理
「ブログを書こうと思ったけど、うまく書けないから公開できない…」
「部屋の片づけ、完璧にできる時間がないからもう少し後で…」
何かを始めようとするとき、「完璧にできないなら、やらない方がマシ」と思ってしまうことはありませんか?これは「完璧主義行動停止型」の心理パターンです。
「子どもにいい親でありたい」という思いが逆効果になるメカニズム
ひとり親として「子どもにいい親でありたい」「すべてをきちんとこなせる親でありたい」という思いが強いほど、この完璧主義の罠にはまりやすくなります。特に、一人で子育てをしていると、「失敗できない」というプレッシャーを感じやすいものです。
心理学の研究によれば、完璧主義には「適応的完璧主義」と「不適応的完璧主義」があります[8]。高い基準を持ちながらも柔軟性がある前者は成長につながりますが、厳格すぎる基準と失敗への恐れを持つ後者は、行動そのものを妨げてしまいます。
ひとり親の場合、周囲の目を気にして「すべてうまくいっているところを見せなければ」と思いがちです。しかし、その思いが強すぎると、かえって一歩を踏み出せなくなってしまうのです。
ひとり親に効果的な「50%ルール」と「下書きフェーズ分離」
この心理パターンに効果的なのが「50%ルール」です。これは、まず半分の完成度でOKと自分に許可を出すというもの。完璧な100%を目指すのではなく、「とりあえず50%でいいや」と割り切るんです。
たとえば、部屋の片づけなら「全部きれいにする」のではなく「とりあえずリビングのテーブルの上だけ片す」。ブログ記事なら「完璧な文章」ではなく「とにかく3行書く」というように。
B.J. Fogg氏によれば、目標達成のハードルを下げることで、実際の行動率が大幅に改善されると述べています[9]。完璧を求めるよりも、「まずはやってみる」という姿勢が、結果的には多くのことを成し遂げる近道なのです。
もうひとつ効果的なのが「下書きフェーズの分離」です。最初から完成形を目指すのではなく、「今日は下書きだけ」と位置づけるんです。完成を求めないことで、心理的なプレッシャーが軽減されます。
子どもと一緒に「失敗OK文化」を育む家庭づくり
完璧主義の克服は、家庭文化の形成にもつながります。「失敗してもOK」という文化を子どもと一緒に育むことで、親自身も完璧であることへのプレッシャーから解放されます。
実際、子どもの前で親が失敗を認め、それを学びに変える姿を見せることは、子どもの成長マインドセットの形成に良い影響を与えるとされています[10]。完璧を目指すよりも、失敗から学び続ける姿勢を大切にする家庭環境が、親子ともに健全な成長をもたらすのです。
対処法として効果的なのは:
- 50%ルール: まず半分の完成度でOKとする
- 下書きフェーズ分離: 「完成版」ではなく「下書き」と位置づける
- If-Thenプランニング: 「もし完璧を求め過ぎたら、深呼吸して一旦休憩する」などのルールを事前に決めておく
完璧主義の最大の問題点は、行動そのものを妨げてしまうこと。「完璧な親」を目指すのではなく、「十分に良い親」であることを許してあげましょう。子どもにとっても、失敗を恐れず挑戦する親の姿は、大切な学びになります。
「一人じゃないよ」同じ悩みを持つひとり親の方と今すぐつながれ、本人確認必須の無料アプリ(2,400名程度が利用中) >>
大切なことを先延ばしにしてしまうとき ― 先延ばし(プロクラスト)型の心理
「今日は疲れたから明日やろう…」
「SNSをチェックしてからにしよう…」
自分にとって本当に大切なことなのに、なぜかついつい後回しにしてしまう。そんな経験はありませんか?これは「先延ばし型」の心理パターンです。
スマホやSNSに逃避しがちなひとり親の心理的背景
ひとり親の場合、子どもが寝た後の貴重な「自分時間」。でも、疲れていると「明日やろう」とついつい思ってしまいます。そして気づけば、スマホを見ているうちに時間が過ぎてしまいます。
この先延ばし行動は、単なる「怠け心」ではないことが心理学研究で明らかになっています。実は、避けている行動に対する「不安」や「苦手意識」が背景にあることが多いのです[11]。
また、ひとり親特有の「頑張りすぎ症候群」も関係しています。昼間は子どものため、仕事のために全力で頑張り、夜になると疲労とストレスから「ご褒美」としてスマホやSNSに逃避してしまうのです。これは心理的な自己防衛反応の一つでもあります。
短時間でも効果的な「タイムボクシング」テクニックの実践法
先延ばし行動の面白いところは、始めるまでのハードルは高いのに、いったん始めると意外と続けられることが多いという点です。つまり、「始める」ためのひと押しが必要なんです。
そこで効果的なのが「タイムボクシング」という方法。これは、短い時間(たとえば15分)だけタイマーをセットして、その間だけ集中するというものです。
たとえば、「英語の勉強を15分だけやる」「オンライン講座を15分だけ見る」などと決めて、タイマーをセット。たった15分なら、疲れていてもなんとかできそうな気がしませんか?
研究によれば、この「時間制限」があることで脳が目標達成モードに切り替わり、集中力が高まる効果があります[12]。また、「15分で終わる」という安心感が、始めるハードルを下げるのです。
子どもが寝た後の15分を最大限活用するための環境デザイン
先延ばしを防ぐもう一つの重要な方法が「環境デザイン」です。誘惑を減らし、目標とする行動を始めやすくする環境を作ることが大切です。
たとえば、スマホを別の部屋に置いたり、通知をオフにしたり。また、前の晩に勉強道具や運動着を出しておくなど、「始める」ためのハードルを下げる工夫をします。
心理学では「行動のトリガー」を設定することの重要性が指摘されています[13]。例えば「子どもが寝た後、お茶を入れたらすぐに英語の教材を開く」というように、特定の行動の後に目標行動を習慣づける方法です。
対処法として効果的なのは:
- タイムボクシング: 15分などの短時間タイマーで強制スタート
- 環境デザイン: スマホを別室に置く、通知をオフにするなど誘惑を減らす
- 報酬設定: 15分取り組んだら、好きなお茶を飲むなど小さな褒美を用意する
「明日から本気出す」という呪文から抜け出すには、まず「今日、少しだけ」という小さなステップから。たった15分の積み重ねが、大きな変化につながります。
あなたの心理パターンについてもっと詳しく知りたい場合は、ペアチルの相談掲示板「ペアチルの泉」で質問してみましょう。AIとひとり親からの多角的なアドバイスが得られます。
「一人じゃないよ」同じ悩みを持つひとり親の方と今すぐつながれ、本人確認必須の無料アプリ(2,400名程度が利用中) >>
「どうせうまくいかない」と思い込んでいるとき ― 学習性無力感型の心理
「前も挑戦したけど、うまくいかなかった…今度も同じだろうな」
「いくら頑張っても状況は変わらない気がする…」
過去の経験から「何をやっても無駄」と思い込み、新しいことに挑戦する意欲を失ってしまうことはありませんか?これは「学習性無力感型」と呼ばれる心理パターンです。
ひとり親特有の挫折体験と自己効力感の関係
ひとり親としての道のりは、時に厳しく孤独なものです。支援制度を申請しても断られた経験、仕事と育児の両立に挫折した経験、人間関係で傷ついた経験…。そんな経験が積み重なると、「何をやっても状況は変わらない」という無力感が生まれやすくなります。
心理学者のマーティン・セリグマンが提唱した「学習性無力感」の理論によれば、人は繰り返し制御不能な状況に置かれると、「何をしても無駄だ」と学習してしまうのです[14]。
ひとり親の場合、社会的支援の不足や偏見、経済的困難など、自分の力ではコントロールできない要因が多いため、この無力感を感じやすい環境にあります。しかし、この感覚は「学習された」ものであり、「学び直し」が可能なのです。
「できなかったこと」ではなく「できたこと」に焦点を当てる記録法
この心理パターンを克服するために効果的なのが「成功体験の再構築」です。これは、過去のわずかな成功体験に目を向け、それを思い出す習慣をつけるというもの。
具体的には、小さなノートを用意して「成功ノート」を作ってみましょう。そこには、過去にうまくいったこと、乗り越えられた困難、小さくてもあなたが達成できたことを書き出します。子育てで工夫してうまくいったこと、仕事で評価されたこと、自分自身の小さな成長…どんな小さなことでも構いません。
ポジティブ経験の記録は主観的幸福感を高めると複数の介入研究で報告されています[15]。そして、この自己効力感が高まることで、新しい挑戦に踏み出す勇気が生まれるのです。
子育ての中の小さな成功体験を再発見するための「成功ノート」
具体的な実践方法として、毎晩寝る前に「今日できたこと」を3つノートに書く習慣をつけてみましょう。最初は「特に何もできなかった」と感じるかもしれませんが、続けるうちに小さな成功に気づけるようになります。
例えば:
- 朝、時間通りに子どもを学校に送り出せた
- 仕事でミスなく一つのタスクを完了した
- 子どもと10分でも笑顔で会話できた
これらはどれも「当たり前」のことに見えるかもしれませんが、ひとり親の忙しい生活の中で、これらをこなしていること自体が素晴らしい成功なのです。
また、「エビデンス列挙」という方法も効果的です。これは「できたこと」の具体的な証拠を集めること。例えば、仕事で受けた感謝のメール、子どもの成長を示す写真、自分の小さな成長の記録など。これらは「私にもできる」という自信の具体的な証拠となります。
対処法として効果的なのは:
- 成功体験の再構築: 過去の小さな成功を書き出し、意識的に思い出す習慣をつける
- エビデンス列挙: 「できたこと」の事実を具体的に書き出す
- 成功パターンの再現: 過去にうまくいった方法を意識的に再現してみる
過去のつらい経験から学ぶことは大切ですが、同時に成功体験にも目を向けることで、少しずつ「私にもできる」という自信を取り戻していきましょう。あなたはすでに多くのことを乗り越えてきているのです。
「一人じゃないよ」同じ悩みを持つひとり親の方と今すぐつながれ、本人確認必須の無料アプリ(2,400名程度が利用中) >>
情報が多すぎて混乱し、行動に移せないとき ― 情報過多混乱型の心理
「どの育児書の方法が正しいのかわからない…」
「キャリアについて調べすぎて、かえって何をすればいいのかわからなくなった…」
情報があふれる現代社会。特に子育てや自己啓発の分野では、次々と新しい情報が押し寄せてきます。そんな情報の洪水の中で、かえって何をすべきかわからなくなってしまう…これは「情報過多混乱型」の心理パターンです。
育児情報の洪水に溺れないためのフィルタリング術
ひとり親の場合、「子育てを一人で担う」というプレッシャーから、より多くの情報を集めようとする傾向があります。ネットで育児情報を検索し、育児書を読み、SNSで他の親のアドバイスを探す…。
しかし、心理学的研究によれば、選択肢や情報が増えすぎると、かえって意思決定が難しくなる「選択のパラドックス」という現象が起きます[16]。情報が多すぎると、脳が処理しきれず、結果的に何も選べなくなってしまうのです。
この状態から抜け出すためには、情報の「フィルタリング」が重要です。すべての情報を取り入れようとするのではなく、信頼できる1〜2つの情報源に絞ることが大切です。
例えば、子育てについては、小児科医のアドバイス、1冊の信頼できる育児書、実際に会ったことのある先輩ママやパパのアドバイスなど、限られた情報源に絞ってみましょう。
ひとり親の限られた時間を最大化する「優先度マトリクス」
情報過多による混乱を防ぐもう一つの方法が、「優先度マトリクス」の活用です。これは、タスクや選択肢を「重要度」と「緊急度」の2軸で分類し、優先順位をつける方法です。
具体的には、紙を4つに区切り、縦軸に「重要」と「重要でない」、横軸に「緊急」と「緊急でない」を書きます。そして、やるべきことや選択肢をそれぞれの象限に振り分けます。
「重要かつ緊急」な事項(子どもの体調不良への対応など)は最優先で。「重要だが緊急でない」事項(子どもの将来の学資準備など)は計画的に。「緊急だが重要でない」事項(急な雑用など)は可能なら委託や簡略化を。「重要でも緊急でもない」事項は思い切って省略するか後回しに。
この方法を使うことで、本当に注力すべきことが明確になり、情報過多による混乱を防ぐことができます。時間管理の研究でも、この方法の有効性が確認されています[17]。
「これだけやればOK」と決める思考法で心の余裕を取り戻す方法
情報過多混乱型の対処法として特に有効なのが「ワン・バイ・ワン」の原則です。これは「一度に一つだけ」に焦点を当てる方法。多くのことを同時に考えるのではなく、まず最優先の一つだけを選んで取り組みます。
そして、「これだけやればOK」という基準をあらかじめ決めておくことも大切です。例えば「今日は英単語を10個覚えればOK」「子どもの勉強は30分見てあげればOK」というように、明確な終了点を設定します。
これにより、「もっとやらなきゃ」というプレッシャーから解放され、心の余裕を取り戻すことができます。完璧を目指すのではなく、「十分に良い」基準を設定することの重要性は、心理学研究でも支持されています[18]。
対処法として効果的なのは:
- 意思決定マトリクス: 重要度×緊急度でタスクを分類
- ワン・バイ・ワン: 優先度1位のタスクのみに集中
- 情報インプット制限: 1つの情報源・教材に絞る
選択肢が多すぎることによる混乱は、現代社会では誰もが経験する課題です。特に時間とエネルギーが限られているひとり親の方には、「選ぶ」より「絞る」ことが大切です。情報を絞り、優先順位をつけ、一つずつ進んでいくことで、心の余裕を取り戻していきましょう。
「一人じゃないよ」同じ悩みを持つひとり親の方と今すぐつながれ、本人確認必須の無料アプリ(2,400名程度が利用中) >>
SNSの「完璧な親」と自分を比べて落ち込むとき ― 他者比較自己否定型の心理
「SNSで見かける他のママ・パパは、こんなにも輝いているのに…」
「あの人は仕事も子育ても完璧にこなしているのに、私はどうしてこんなに大変なんだろう…」
SNSで見かける「完璧な子育て」「理想の家庭」の投稿。それを見て自分と比較し、落ち込んでしまった経験はありませんか?これは「他者比較自己否定型」の心理パターンです。
ソーシャルメディアがひとり親の自己評価に与える影響
ソーシャルメディア上では、多くの人が「ハイライト」だけを投稿しています。楽しい家族旅行、子どもの成功体験、きれいに整えられた食卓…。しかし、その裏にある日常の苦労や葛藤は見えません。
研究によれば、SNSの過度な使用は自己評価の低下やうつ症状との関連が指摘されています[19]。特に、他者の「編集された人生」と自分の「リアルな日常」を比較すると、自己否定感が強まりやすいのです。
ひとり親の場合、この比較の罠にはまりやすい傾向があります。「二人親家庭」の見栄えのする投稿を見て、自分の状況と比べてしまったり、「同じひとり親なのに、あの人はなんでうまくいっているんだろう」と思ってしまったり。
しかし、SNS上の「完璧な親」像は多くの場合、現実とはかけ離れた一部分でしかないのです。
「今日の自分」と「昨日の自分」だけを比べる自己比較の習慣づけ
この心理パターンを乗り越えるために効果的なのが「自己比較」の習慣です。他者と比べるのではなく、「昨日の自分」と「今日の自分」だけを比較することで、自分の成長や変化に目を向けます。
具体的には、毎日または毎週の振り返りを習慣にします。「今週できるようになったこと」「先週よりも上手くいったこと」「少し成長を感じた点」などを記録するのです。
研究によれば、この自己比較の習慣は、自己効力感の向上と自己肯定感の強化につながります[20]。他者という不確かな基準ではなく、自分自身の変化という確かな基準で自己評価することで、より健全な自己認識が育まれるのです。
ひとり親同士のリアルなつながりが自己肯定感を高める理由
SNSの「編集された現実」ではなく、リアルな人間関係の中でこそ、本当の自己肯定感が育まれます。特に、同じひとり親同士のつながりは大きな支えになります。
心理学研究でも、同じ境遇の人とつながることで「共感」「連帯感」「所属感」が生まれ、それが精神的健康に良い影響を与えることが示されています[21]。
同じ苦労を知る人と話すことで「私だけじゃないんだ」と感じられる安心感。成功体験も失敗談も包み隠さず共有できる関係。そんなリアルなつながりの中でこそ、自分を否定せず受け入れる感覚が育まれるのです。
対処法として効果的なのは:
- リフレーミング: 「SNSは現実の一部でしかない」と意識的に捉え直す
- ジャーナリング: 毎日「今日の自分の成長」を3行で記録する
- ソーシャルメディア断ち: 比較を避けるため一定期間SNS利用を控える
他者との比較は時に成長のきっかけになることもありますが、自己否定のサイクルに陥るようであれば、思い切ってSNSとの距離を置くことも検討してみましょう。そして、「今日の自分」と「昨日の自分」だけを比べる習慣を育てることで、少しずつ自分自身を認められるようになっていきます。
「一人じゃないよ」同じ悩みを持つひとり親の方と今すぐつながれ、本人確認必須の無料アプリ(2,400名程度が利用中) >>
「もう年だから」「才能がない」と思いがちなとき ― 固定的マインドセット型の心理
「子どもの英語教育は大切だけど、私自身はもう新しい言語を学ぶには年をとりすぎた…」
「数学が苦手だから、子どもの宿題を見てあげられない…」
新しいことに挑戦するとき、「自分には才能がない」「年齢的に無理」などと決めつけてしまうことはありませんか?これは「固定的マインドセット型」の心理パターンです。
「子育てで手一杯」という現実と成長マインドセットの両立法
ひとり親の方々は、日々の子育てや仕事に追われる中で「新しいことを学ぶ余裕がない」と感じることも多いでしょう。確かに時間的制約は現実問題として存在します。
しかし、スタンフォード大学の心理学者キャロル・ドゥエックの研究によれば、私たちの能力や才能に対する考え方(マインドセット)は、大きく二つに分けられます[22]。
一つは「固定的マインドセット」。能力は生まれつき決まっていて、努力してもあまり変わらないという考え方です。もう一つは「成長マインドセット」。能力は努力や適切な学習方法によって伸ばせるという考え方です。
「子育てで手一杯」という現実を認めつつも、小さな範囲で「成長マインドセット」を取り入れることは可能です。例えば、15分だけ新しい言語の学習アプリを使ってみる、子どもと一緒に算数の問題に取り組むなど、「完全にマスター」ではなく「少しずつ向上」を目指す姿勢が大切です。
子どもの前で「学び続ける親」でいることの大切さ
実は、親が「学び続ける姿勢」を見せることは、子どもの教育において非常に重要です。子どもは親の行動を観察し、それをモデルとして学びます。
研究によれば、親が成長マインドセットを持っていると、子どもも同様のマインドセットを発達させる傾向があります[23]。「お母さん(お父さん)も新しいことに挑戦している」という姿を見せることで、子どもに「挑戦する勇気」「失敗から学ぶ姿勢」を自然と教えることができるのです。
「完璧な親」を演じるよりも、「成長し続ける親」でいることが、子どもの健全な成長を促すのです。
脳科学から見た「いくつになっても成長できる」という希望の科学
「年齢的にもう無理」という考えは、実は科学的に正確ではありません。脳科学の研究によれば、脳は生涯にわたって変化し続ける「可塑性」を持っています[24]。
ニューロプラスティシティ(神経可塑性)と呼ばれるこの特性により、私たちの脳は年齢に関わらず、新しい神経回路を形成し、新たなスキルを習得することができるのです。確かに年齢によって学習のスピードや方法は変わりますが、「学ぶ能力」自体は失われることはありません。
ある研究では、80代の高齢者でも適切なトレーニングによって記憶力や認知機能を向上させることができたという結果も報告されています[25]。年齢は学びの障壁ではなく、単に異なるアプローチが必要なだけなのです。
対処法として効果的なのは:
- 成長マインドセット教育: 「まだできない」ではなく「まだできない」という言い方に変える
- プロセス称賛: 結果ではなく「努力・戦略・粘り強さ」を自分自身で評価する
- 脳の可塑性学習: 脳が生涯変化し続けることについて学ぶ
「もう遅い」「私には才能がない」という思い込みは、科学的に見ると正確ではありません。年齢や生まれつきの才能よりも、「学び続ける姿勢」「適切な学習方法」「継続的な実践」が、能力向上の鍵となるのです。
このことを理解し、子どもと一緒に成長し続ける親でいることが、あなた自身の人生も、子どもの未来も豊かにしていくでしょう。
「一人じゃないよ」同じ悩みを持つひとり親の方と今すぐつながれ、本人確認必須の無料アプリ(2,400名程度が利用中) >>
変化によって「自分らしさ」が失われる不安 ― アイデンティティ脅威型の心理
「もっと自己主張すべきかもしれないけど、それが本当の私なのかな…」
「新しいキャリアに挑戦したいけど、今の『ママ』としての自分が変わってしまいそうで怖い…」
自分を変えたいと思いながらも、変化によって「本当の自分」が失われてしまうのではないかという不安を感じることはありませんか?これは「アイデンティティ脅威型」の心理パターンです。
「母親(父親)」「仕事人間」など、固定的な自己イメージから解放される方法
ひとり親になると、「母親(父親)」という役割が生活の中心になりがちです。また、経済的な理由から「仕事人間」としてのアイデンティティが強くなることもあります。そうした役割が自分のアイデンティティの大部分を占めるようになると、それ以外の側面を発展させることへの心理的抵抗が生まれます。
アイデンティティ研究によれば、人間のアイデンティティは複数の側面を持つ多面的なものです[26]。「親」「仕事人」「友人」「趣味人」「学び手」など、様々な側面があり、それらが調和して全体としての「自分」を形作っています。
しかし、特定の役割に過度に同一化すると、他の側面を発展させることに抵抗を感じてしまいます。この状態から抜け出すためには、「自己概念の拡張」が有効です。これは、新たな側面を「追加」するものであり、既存の自分を「否定」するものではないと捉えることです。
例えば、「母親であり、かつ学び手でもある私」「仕事人間であり、かつ趣味を楽しむ私」というように、「AであってBでもある」という包括的な自己概念を育てていくのです。
子どもと一緒に成長する「進化する親」という新しい自己物語
アイデンティティ脅威を乗り越えるもう一つの方法が「ナラティブ再構築」です。これは、自分の人生や自己イメージについての「物語」を書き換えるプロセスです。
特に有効なのが「進化する親」という自己物語です。「完璧な親」や「犠牲的な親」ではなく、「子どもと共に成長し、変化し続ける親」という自己イメージを育てるのです。
心理学的研究によれば、このような「成長指向」の自己物語を持つことは、アイデンティティの柔軟性と心理的なレジリエンス(回復力)を高めるとされています[27]。
子育ては一方的に子どもを育てるプロセスではなく、親自身も成長し変化するプロセスであると捉えることで、変化への抵抗が和らぎます。
ひとり親としての強みを活かした自己イメージの拡張法
ひとり親であるということは、多くの課題がある一方で、特有の強みも育まれています。例えば、問題解決能力、時間管理能力、レジリエンス(回復力)、決断力などです。
これらの強みを意識的に認識し、新たな挑戦の基盤として活用することで、自己イメージを拡張していくことができます。
具体的には、「価値観明確化」という方法が有効です。自分にとって本当に大切な価値観(例えば「成長」「挑戦」「創造性」「つながり」など)を特定し、それを基準に新たな選択をしていくのです。
研究によれば、自分の深い価値観に基づいた行動をとることは、アイデンティティの一貫性を保ちながらも成長を促すとされています[28]。
対処法として効果的なのは:
- 自己概念の拡張: 新たなアイデンティティを既存の自己に「追加」と捉える
- 価値観明確化: 根底にある大切な価値観を特定し、それを維持した変化を検討
- ナラティブ再構築: 「成長する自分」を含む新しい自己物語を創造
変化することは「本当の自分」を失うことではなく、むしろ「より豊かな自分」を発見するプロセスです。ひとり親としての経験と強みを基盤に、少しずつ自己イメージを拡張していくことで、より自由で柔軟な「自分らしさ」を育んでいくことができるでしょう。
「一人じゃないよ」同じ悩みを持つひとり親の方と今すぐつながれ、本人確認必須の無料アプリ(2,400名程度が利用中) >>
心も体も疲れ果ててしまったとき ― 燃え尽き症候群型の心理
「以前は子育ても仕事も意欲的だったのに、最近はただこなすだけ…」
「何をやっても楽しくない。何も変える気力が湧いてこない…」
毎日の責任を一人で背負い続けるひとり親の方々。いつしか心も体も疲れ果て、何も変える意欲が湧かない状態になることがあります。これは「燃え尽き症候群型」の心理パターンです。
ひとり親の「頑張りすぎサイン」と早期発見のチェックポイント
燃え尽き症候群(バーンアウト)は、長期間のストレスや過度の責任により、心身のエネルギーが枯渇した状態を指します。特にひとり親の場合、サポート不足や休息の機会の少なさから、この状態に陥りやすい傾向があります。
世界保健機関(WHO)は、燃え尽き症候群を「慢性的な職場ストレスが上手く管理できないことに起因する症候群」と定義しています[29]。ひとり親の場合は、「職場」だけでなく「家庭」でのストレスも重なるため、より複雑な燃え尽き状態になりがちです。
早期発見のためのチェックポイントとしては:
- 慢性的な疲労感が続いている
- 以前は楽しめていたことに興味や喜びを感じなくなった
- イライラしやすくなった、または逆に感情が鈍くなった
- 眠れない、または逆に寝すぎる
- 小さなミスや忘れ物が増えた
- 「これ以上頑張れない」という無力感がある
これらの症状が複数当てはまる場合は、燃え尽き症候群の初期段階かもしれません。早めの対処が重要です。
「自分を充電する時間」を確保するための現実的な方法
燃え尽き症候群の対処法として最も重要なのが「エネルギー管理」です。これは、限られたエネルギーを効率的に使い、意識的に回復する時間を確保することです。
ひとり親の忙しい生活の中でも実践できる現実的な方法としては:
- マイクロブレイク: 1日の中で数分間の小休憩を意識的に取る。例えば、子どもが遊んでいる間の5分、お茶を飲みながら深呼吸するなど。
- 優先順位の見直し: 「完璧にこなす」ことを諦め、「最低限必要なこと」と「あれば理想的なこと」を明確に分ける。とくに家事などは思い切って基準を下げることも大切。
- 「NO」と言う練習: 新たな責任や約束を引き受ける前に「これは本当に必要か」を自問する習慣をつける。不要不急のものには丁寧に断る。
- 充電活動の特定: 自分がエネルギーを回復できる活動(読書、入浴、散歩、趣味など)を特定し、短時間でも定期的に行う。
心理学的研究でも、小さな「自己充電」の習慣が、燃え尽き症候群の予防と回復に効果的であることが示されています[30]。完全休養の時間が取れなくても、日常の中の小さな充電習慣が大きな違いを生むのです。
「子どものため」と「自分のため」は矛盾しないことを理解する考え方
燃え尽き症候群を乗り越える上で重要な心の転換は、「子どものため」と「自分のため」を対立させない考え方です。この二つは実は矛盾せず、むしろ相互に支え合う関係なのです。
心理学者のドナルド・ウィニコットは「ほどよい母親(good enough mother)」という概念を提唱しました[31]。これは、完璧な親を目指すのではなく、十分に良い親であることを認める考え方です。
実際、親が自分自身を大切にし、心身の健康を保つことは、結果的に子どもにとっても最大の利益になります。疲弊した親よりも、エネルギーに満ちた親の方が、より質の高い時間を子どもと過ごせるからです。
飛行機の安全指示で「まず自分に酸素マスクを装着してから、子どもを助ける」と言われるように、親が自分を大切にすることは、子どもを守るための前提条件なのです。
対処法として効果的なのは:
- エネルギー管理: 回復期間の確保と適切な休息
- 価値再評価: 本当に大切なことを見直し、優先順位づけ
- 小さな喜びの再発見: 日常の中での小さな楽しみを意識的に取り入れる
燃え尽き症候群からの回復は一朝一夕には進みませんが、小さな自己ケアの積み重ねが大きな変化を生み出します。自分を大切にすることが、結果的に子どもの幸せにもつながることを信じて、少しずつ回復の歩みを進めていきましょう。
「一人じゃないよ」同じ悩みを持つひとり親の方と今すぐつながれ、本人確認必須の無料アプリ(2,400名程度が利用中) >>
理想と現実のギャップに苦しむとき ― 認知的不協和型の心理
「ひとり親になる前に描いていた生活と、今の現実があまりにも違う…」
「子どもにもっと豊かな経験をさせてあげたいのに、現実は毎日の生活で精一杯…」
理想と現実のギャップに心が引き裂かれるような感覚。「こんなはずじゃなかった」という思いに苦しむことはありませんか?これは「認知的不協和型」の心理パターンです。
「こんなはずじゃなかった」という思いと上手に付き合う方法
認知的不協和とは、心理学者レオン・フェスティンガーが提唱した概念で、二つの矛盾する考えや信念を同時に抱えることで生じる心理的な不快感を指します[32]。
ひとり親の場合、「理想の親像」と「現実の自分」の間のギャップ、「子どもに与えたい生活」と「提供できる現実」の差、「描いていた人生設計」と「現在の状況」の違いなど、様々な不協和が生じやすい状況にあります。
この不快感を解消するために、人は通常、どちらかの考えを変えようとしますが、それがうまくいかないと、慢性的なストレスや自己否定感につながってしまいます。
対処法として効果的なのは「認知的調和の再構築」です。これは、矛盾するように見える二つの信念や価値観の間に、新たな調和点を見出すプロセスです。
例えば:
- 「完璧な親」と「限界のある現実の自分」の間に「成長し続ける親」という新たな自己像を見出す
- 「子どもに与えたい豊かな経験」と「経済的制約」の間に「創意工夫で作り出す特別な時間」という価値を見出す
- 「描いていた人生設計」と「現在の状況」の間に「予想外の成長機会」という意味を見出す
心理学研究によれば、このような「意味の再構築」は、逆境からの回復力(レジリエンス)を高めることが示されています[33]。
ひとり親としての「今ここ」を受け入れるマインドフルネスの実践
認知的不協和に対処するもう一つの効果的な方法が「マインドフルネス」です。これは、過去や未来への思考に捕らわれず、「今この瞬間」に意識を向ける実践です。
マインドフルネスの研究によれば、「今ここ」に意識を向けることで、ストレスが軽減し、感情調整能力が向上することが示されています[34]。特に、「理想と現実のギャップ」に苦しんでいる場合、過去の期待や未来の不安から距離を置き、現在の瞬間に意識を向けることが心の安定につながります。
実践方法としては:
- 1日に数分間、静かに座って呼吸に意識を向ける
- 日常の活動(食事、歩行、子どもとの会話など)を意識的に「今ここ」に焦点を当てて行う
- 感情や思考を「良い/悪い」と判断せず、ただ観察する習慣をつける
ひとり親の忙しい日常の中でも、短時間のマインドフルネスを取り入れることで、心の安定感が増し、理想と現実のギャップによる苦しみが和らぐことが期待できます。
新しい人生の物語を描き直す「ナラティブ・シフト」のテクニック
認知的不協和を乗り越える最も効果的な方法の一つが「ナラティブ・シフト」です。これは、自分の人生や状況についての「物語」を書き換えるプロセスです。
心理学者マイケル・ホワイトらが開発したナラティブ療法の考え方によれば、人は自分自身や人生について「物語」を構築し、その物語を通して経験を理解しています[35]。問題が生じるのは、ネガティブで制限的な物語に捕らわれたときです。
ナラティブ・シフトでは、既存の物語を書き換え、新たな意味や可能性を見出していきます。例えば:
- 「失敗の物語」→「学びと成長の物語」
- 「犠牲の物語」→「強さと回復力の物語」
- 「欠如の物語」→「創意工夫と適応の物語」
具体的な実践方法としては、日記やジャーナリングを通して自分の経験を「書き換える」ことが有効です。特に、困難な経験の中にも意味や価値、成長の機会を見出す書き方を意識してみましょう。
対処法として効果的なのは:
- 認知的調和の再構築: 変化と既存の価値観の一致点を見出す
- マインドフルネス実践: 「今ここ」に意識を向け、過去や未来への執着を緩める
- ナラティブ・シフト: 人生の物語を書き換え、新たな意味や可能性を見出す
理想と現実のギャップは誰もが経験するものですが、特にひとり親の方々は大きなギャップに直面しがちです。しかし、そのギャップそのものを「成長の機会」「新たな可能性の発見」として捉え直すことで、苦しみを変容させていくことができるのです。
「一人じゃないよ」同じ悩みを持つひとり親の方と今すぐつながれ、本人確認必須の無料アプリ(2,400名程度が利用中) >>
あなたの心理パターンを知って、小さな一歩を踏み出すために
ここまで、自己変容を妨げる10の心理パターンとその対処法を見てきました。ここからは、これらの知識をどのように活用して、実際の一歩を踏み出していくかについて考えていきましょう。
セルフチェックであなたの心理パターンを確認してみよう
まずは、自分がどの心理パターンの影響を受けやすいのかを知ることが大切です。以下のチェックリストを使って、自己診断してみましょう。当てはまる項目が3つ以上あるパターンは、あなたの自己変容を妨げている可能性があります。
自己変容放棄型チェック
□ 新しいことに挑戦する前に「自分には無理」と決めつけることが多い
□ 過去の経験から「これ以上の努力は無駄」と考える
□ アドバイスをもらっても「それは他の人には効くかもしれないが自分には無理」と思う
□ 「今の自分でいい」「このままでいい」と現状維持を選ぶことが多い
□ 「もう頑張っている」という言葉をよく使う
完璧主義行動停止型チェック
□ 失敗するくらいなら始めない方がましだと考える
□ 「100%できないなら0%と同じ」と思うことがある
□ 下書きや未完成の状態を人に見せることに強い抵抗がある
□ やり直しが効かない状況で極度に緊張する
□ 「こんな出来では恥ずかしい」と思うことが多い
先延ばし(プロクラスト)型チェック
□ 重要なことを後回しにして、どうでもいいことに時間を使うことが多い
□ 「今はその気分じゃない」とよく言う
□ 期限ギリギリまで動き出せないことが多い
□ 着手すれば簡単なことも、始めるまでに異常に時間がかかる
□ SNSやネットサーフィンで気づくと時間が経っていることが多い
学習性無力感型チェック
□ 「どうせうまくいかない」と事前に諦めることが多い
□ 過去の失敗体験がトラウマのように感じられる
□ 「努力しても報われない」と思うことがある
□ 何かを始める意欲自体が湧かない
□ 「自分に何ができるのだろう」とよく考える
情報過多混乱型チェック
□ 選択肢が多すぎて決断できないことがよくある
□ 「もっと調べてから」と行動を先延ばしにする
□ 情報を集めることと行動することの区別があいまい
□ 本やネット記事を読むのは好きだが実践は少ない
□ 「どれが正解か分からない」と悩むことが多い
他者比較自己否定型チェック
□ SNSで他者の成功を見ると落ち込むことが多い
□ 「あの人はできるのに、なぜ自分は…」とよく考える
□ 他者の評価を過度に気にする
□ 自分の成功を「運が良かっただけ」と矮小化する
□ 他者の目を意識し過ぎて自分の判断が鈍る
固定的マインドセット型チェック
□ 「頭の良さは生まれつき決まっている」と思う
□ 失敗を「自分に才能がない証拠」と捉える
□ 努力することより「才能がある」と思われたい
□ 新しいスキルの習得に「もう遅い」と感じる
□ 批判やフィードバックを個人攻撃と受け取りがち
アイデンティティ脅威型チェック
□ 変化すると「自分らしさを失う」と不安になる
□ 「〇〇な自分」という自己イメージに強くこだわる
□ 周囲の期待に応えられなくなることを恐れる
□ 変化により大切な人間関係が損なわれると心配する
□ 新しい自分に違和感や居心地の悪さを感じる
燃え尽き症候群型チェック
□ 以前は熱中していたことにも興味が持てなくなっている
□ 慢性的な疲労感や意欲低下を感じる
□ 「頑張っても報われない」と感じることが多い
□ 小さなことにもイライラしたり無気力になったりする
□ 休んでも回復した感覚が得られない
認知的不協和型チェック
□ 変化が自分の価値観や信念と矛盾すると感じる
□ 「こんなはずじゃなかった」と思うことが多い
□ 期待と現実のギャップに強いストレスを感じる
□ 理想の自分像と現実の行動の不一致に苦しむ
□ 変化を受け入れると自己矛盾を感じる
いくつかのパターンに当てはまったとしても、それは珍しいことではありません。多くの人、特にひとり親の方々は複数のパターンを持っています。大切なのは、自分を責めるのではなく、理解すること。そして、小さな一歩から変化を始めることです。
「一人じゃないよ」同じ悩みを持つひとり親の方と今すぐつながれ、本人確認必須の無料アプリ(2,400名程度が利用中) >>
全てのパターンに共通する「小さな一歩の法則」
10のパターンにはそれぞれ特有の対処法がありますが、すべてに共通する重要な原則があります。それが「小さな一歩の法則」です。
行動科学の研究によれば、持続的な変化を生み出すために最も効果的なのは、大きな目標を設定することではなく、「超小型の習慣(Tiny Habits)」を積み重ねることだとされています[36]。
スタンフォード大学の行動科学者B.J.フォッグ教授は、行動変容を成功させるポイントとして以下の3つを挙げています:
- 極小の目標設定: 「30分運動する」ではなく「1分だけストレッチする」など、とにかく小さな目標を設定する
- 既存の習慣に紐づける: 「コーヒーを入れた後に、1分間の深呼吸をする」など、すでにある習慣の後に新しい小さな習慣をつなげる
- 成功を祝う: 小さな目標を達成したら、心の中で「やった!」と自分を称える
この「小さな一歩の法則」は、特に時間とエネルギーが限られているひとり親の方々にとって、非常に実践的なアプローチです。
「変化」という大きな山を前にして圧倒されるのではなく、まずは本当に小さな一歩を踏み出すこと。それを毎日積み重ねることで、少しずつでも確実に変化していくことができるのです。
ひとり親だからこそ、自分を大切にする時間が子どもの幸せにつながる理由
最後に、なぜひとり親にとって「自分を大切にする時間」が特に重要なのかについて考えてみましょう。
心理学研究によれば、親の精神的健康状態は、子どもの発達と幸福感に直接的な影響を与えることが示されています[37]。特にひとり親家庭では、親が唯一または主要な育児担当者であるため、その影響はより大きくなります。
自分自身を大切にし、自己成長の時間を持つことは、単なる「自分のため」の行為ではありません。それは同時に子どもに以下のような恩恵をもたらします:
- ポジティブなロールモデルの提供: 自分を大切にし、成長し続ける親の姿は、子どもにとって強力なロールモデルとなります。「大人になるとは、学び続け、成長し続けることなんだ」という価値観を自然と伝えることができます。
- 質の高い親子時間の実現: 精神的に充実した親は、子どもとの時間もより質の高いものになります。疲弊した状態では、物理的に一緒にいても、心理的には「不在」になりがちです。自己充電することで、「心から一緒にいる」時間を提供できます。
- 子どもの自立性と回復力の育成: 親が常に自己犠牲的であると、子どもは無意識のうちに「罪悪感」を感じることがあります。一方、親が適切に自分の時間を持ち、自己成長を図ることで、子どもも健全な自立性と心理的な回復力を発達させやすくなります。
「親の幸せが第一」という考え方は、一見すると利己的に思えるかもしれません。しかし実際には、それが子どもの幸せにもつながる「Win-Win」の選択なのです。
自分を変え、成長させることへの一歩は、自分自身のためだけでなく、子どもの未来のためでもあるのです。
まとめ
この記事では、ひとり親が自己変容に挑戦するときに直面しがちな10の心理パターンと、それぞれの対処法を紹介してきました。
自己変容を妨げる心理パターンを知ることは、自分を責めるのではなく理解するための第一歩です。「怠け心」や「意志の弱さ」ではなく、心の仕組みによる自然な反応だと理解することで、より効果的な対処法を見つけることができます。
ひとり親の忙しい現実の中でも、「小さな一歩の法則」を活用すれば、持続可能な変化を生み出すことができます。完璧を求めるのではなく、「ほんの少しでも前に進む」という姿勢が、長期的には大きな変化につながるのです。
そして何より、自分自身を大切にすることは、子どもの幸せや成長にもつながる「Win-Win」の選択です。親が充実していることが、子どもにとっての最大の安心感と成長環境になるのです。
同じ境遇の仲間と繋がり、互いに支え合いながら、一歩ずつ成長していく。あなたの小さな一歩が、やがて大きな変化となって、あなた自身と子どもの人生を豊かにしていくことでしょう。
全国の似た境遇のひとり親と繋がれ、子育てや趣味などについて気軽にトークできるアプリ「ペアチル」もぜひご利用ください。すべての機能が無償なため、お守りがわりにお使いください(^ ^)
参考文献
[1] ジェームズ・クリア (2020). 「アトミック・ハビット」
[2] 国立社会保障・人口問題研究所 (2022). 「ひとり親家庭の生活と意識に関する調査」
[3] デイビッド・ロック (2018). 「脳の働きから見た意思決定」
[4] キャロル・ドゥエック (2016). 「マインドセット」
[5] 厚生労働省 (2021). 「ひとり親家庭等の現状について」
[6] アルバート・バンデューラ (1997). 「自己効力感の心理学」
[7] ジョン・ラッティ (2015). 「脳を鍛えるには運動しかない」
[8] ランディ・フロスト (2010). 「完璧主義の心理学」
[9] B.J.フォッグ (2020). 「スタンフォード式最高の習慣術」
[10] キャロル・ドゥエック (2016). 「子どもの可能性を引き出すマインドセット」
[11] スティール (2013(日本語訳)/2011(原著)). 「先延ばしする心の科学」
[12] Francesco Cirillo (2018) 『ポモドーロ・テクニック』
[13] チャールズ・デュヒッグ (2012). 「習慣の力」
[14] マーティン・セリグマン (2013). 「オプティミストはなぜ成功するか」
[15] Anna T. Wisniewski (2021). 「Self-compassion moderates the predictive effects of social media use profiles on depression and anxiety」
[16] バリー・シュワルツ (2004). 「なぜ選ぶたびに後悔するのか」
[17] スティーブン・コヴィー (1996). 「7つの習慣」
[18] ブレネー・ブラウン (2012). 「弱さを力に」
[19] 2021 年 メタ分析 “Does social media use make us happy?”
[20] アルバート・バンデューラ (1997). 「自己効力感の心理学」
[21] アーヴィン・ヤーロム (2012). 「グループサイコセラピー」
[22] キャロル・ドゥエック (2016). 「マインドセット」
[23] デイビス (2018). 「親のマインドセットが子どもに与える影響」
[24] ノーマン・ドイジ (2008). 「脳は変わる」
[25] パーク (2014). 「高齢者の認知トレーニングの効果」
[26] エリク・エリクソン (1989). 「ライフサイクル、その完結」
[27] ダン・マクアダムス (2013). 「ナラティブ・アイデンティティ」
[28] スティーブン・ヘイズ (2019). 「アクセプタンス&コミットメント・セラピー」
[29] 世界保健機関 (2019). 「燃え尽き症候群の定義と特徴」
[30] エレン・ランガー (2002). 「マインドフルネス」
[31] ドナルド・ウィニコット (1986). 「赤ちゃんと母親」
[32] レオン・フェスティンガー (1957). 「認知的不協和の理論」
[33] ビクター・フランクル (1993). 「それでも人生にイエスと言う」
[34] ジョン・カバットジン (2013). 「マインドフルネスストレス低減法」
[35] マイケル・ホワイト (2009). 「ナラティブ実践地図」
[36] B.J.フォッグ (2020). 「スタンフォード式最高の習慣術」
[37] リバーマン (2016). 「親の精神的健康と子どもの発達の関連性」
すべてのコラム
-

コラム
2024.09.19
シングルマザーの生活や仕事を支える66の手当と支援制度を徹底解説!保存して見返そう!
シングルマザーの皆さん、日々の子育てや生活に不安や悩みを抱えていませんか?実はシングルマザーの生活を支える支援制度
-

コラム
2023.10.19
子連れ再婚した元シングルマザーが語る「シングルマザーの再婚成功のための完全ガイド」
こんにちは!元旦那の不倫がきっかけで当時6歳と3歳の子供2人を連れて離婚しました元サレ妻華子です。 私自身、元旦
-

コラム
2023.10.08
【体験談】資格・学歴なし専業主婦のまま離婚して無職危機!?一念発起していろいろと資格を取得したら生活が変わりました
みなさん初めまして!シングルマザーになってから早4年、5歳の子供を育てるぽんたです! 突然ですが、みなさ
-

コラム
2023.09.11
【実体験】ひとり親にとって資格は必要?私のケースや資格取得支援制度4つおすすめの資格7選を紹介!
こんにちは!現在離婚調停中の0歳児を育てるシンママ予備軍の「はのたる」です。 みなさんは現在のご自身の働き方に満
-

コラム
2023.08.14
【体験談】養育費以外で請求可能な特別費用を徹底解説!習い事の費用も?その相場と義務について
こんにちは。元旦那の不倫がきっかけで当時6歳と3歳の子供2人を連れて離婚しました元サレ妻華子です。 離婚
-

コラム
2026.01.14
あなたの隣に住む子どもが、経済的理由でスポーツを諦めているかもしれない|神奈川発「フットサルdeチェンジ」の挑戦
「本当はサッカーをやりたかった。でも、お母さんに言えなかった」 これは、あるひとり親家庭で育った男性の言葉です。
-

コラム
2025.12.04
「何かを得ると何かを失う」5歳児を育てながら転職成功したシングルマザーが語る、やりがいと子育ての優先順位の決め方
こんにちは!ペアチル代表理事の南です。 「転職したいけど、子どもがいると条件が厳しくて…」 「やりがいと子
-

サービス・団体の紹介
2025.09.17
無料どころか2万円もらえる!シングルマザーが安心して挑戦できる介護職への道-株式会社CLACKのジョブトランジットのご紹介-
今日は、シングルマザーのみなさんに、ちょっと驚きの転職支援プログラムをご紹介したいと思います。 「転職した
-

コラム
2025.08.25
夫婦仲が悪いまま我慢すべき?シングルマザー経験者が語る離婚の判断基準と子どもへの影響・改善策
夫婦の仲が悪いと感じた時、ふと「このまま離婚してしまおうか」と悩む人は少なくないはず。しかし、その時に子どものことを思
-

コラム
2025.08.25
シングルマザーだからって夢諦めるの?年子2人育てるシングルマザーの私が思う正解と生き方
シングルマザーのみなさん、いつもお疲れ様です。シングルマザーって大変ですよね。いや?私自身が結構「シングルマザーって大
-

コラム
2025.08.25
シングルマザーが実践!夏休みの家事地獄から抜け出す時短テクと親子時間の作り方。手間を減らす工夫と楽しむポイントを伝授!
夏休みが始まると、家事の量も子どものお世話も一気に増えて「気がつけば1日が終わっている…」という日々に。 現役シ
-

コラム
2025.08.25
シングルマザーと結婚する「本当の」メリットとデメリットを解説。経験者が語る再婚の本音と幸せな家庭を築くためのアドバイス
シングルマザーと話していると、よく話題になります。「私たち、再婚できる?」と。私はそんな雑談の時間が大好きなのですが、
-

コラム
2025.07.28
シングルマザーに友達がいない理由5つと孤独を解消する出会い方!居酒屋からアプリまで実体験で紹介
シングルマザーとして奮闘する中で、ふと孤独を感じる瞬間はありませんか?「友達がいないのは、私だけ?」と不安に思うかもし
-

コラム
2025.07.28
シングルマザーになるメリット7選!夫のお世話・夫婦喧嘩から解放されて幸せになった2児の母の実体験
離婚を考えたとき、「シングルマザーになったら、今よりもっと大変になるのでは…」と、未来への不安でいっぱいになっていませ
-

コラム
2025.06.18
母子家庭の方が金持ち?支援制度フル活用×副業×投資で実現する経済的自由への一歩を解説
「母子家庭は経済的に厳しい」。そんなイメージを覆し、実際に経済的な豊かさを実現している家庭も少なくありません。
-

コラム
2025.06.18
シングルマザーが可愛いと言われる5つの理由!精神的な強さと母性が生む魅力で自信を取り戻す具体的方法
前の恋で傷ついてしまったからこそ、シングルマザーだからって、可愛さを諦めていませんか?「私のことなんて誰も可愛いって思
-

コラム
2025.06.18
シングルマザーの性格がきついは誤解!経済困窮と育児疲労が生む心理的負担と今すぐできる対処法を解説
「シングルマザーは性格がきつい」という言葉を聞いたことはありませんか?あるいは、あなた自身がそう感じたり、言われたりし























